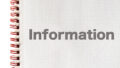三内丸山遺跡の見所
史跡見学
三内丸山遺跡到着後、早速遺跡内へ。
見学記事をまとめるにあたっては、以下の情報を参考にしました。
参考
- 【”たびキュンパス”で三内丸山へ/8】雪景色の青森・三内丸山遺跡
- 三内丸山遺跡公式サイト
- 青森県教育委員会 “特別史跡 三内丸山遺跡”(史跡パンフレット)
- NPO法人三内丸山縄文発信の会 “さんまる探訪 三内丸山遺跡ガイドブック(改訂版)”(ものの芽舎、2021.10.13)
- 東奥日報社『特別史跡 三内丸山遺跡』(2021.9.13)
盛土

案内板にもありますが、盛土とは縄文時代の集落のゴミ捨て場跡です。
毎日の生活で不要となったもの、あるいは柱を立てる際に掘り返した土などが繰り返し詰まれ、小高い丘のようになった場所がそれに該当します。
三内丸山遺跡内には、北・南・西の三か所に盛土があるようです。

南盛土はそのうち一番遺跡の出入り口に近いところにあるので、ガイドツアーでは、ほぼ入って早々に見学する施設となります。

施設内では、盛土が掘り返された状態で保存されているので、

日常生活で使用され、後にゴミとなった土器や石器の欠片などが、分かりやすく可視化されています。
竪穴式住居

三内丸山遺跡では、三内丸山の集落がもっとも繁栄していた縄文時代中期中ごろ(約4800年前)の竪穴住居が復元されています。
床面積は10m2程度、4〜5人程度が暮らしていたと推定される小型のものが多く、三内丸山遺跡内でのこれまでの調査では、その規模の竪穴住居が約800棟程度見つかっています。

そのうちの一棟へ。

中に入ることも出来るようになっているのですが、

半地下となっている住居内は造り自体が結構しっかりしていて、

今でも用途を限定すれば、十分実用に耐えそうに見えます。
実際、同種・同規模の家を「期間限定のアウトドア」感覚で拠点にする分には、めっちゃテンション上がるでしょうね。
掘立柱建物

竪穴式住居の傍に、三棟ほど並んでいるのが見えます。
竪穴式住居同様、三内丸山集落最盛期の縄文中期、今から約4800年前の建物です。
復元されているのは高床式のものですが、平地式のものであった可能性もあるようです。

同じ方向を向き、かつムラの中央部分に建てられていることから、同時期に、墓や埋葬、祭祀・義礼に関連する施設として作られた可能性が指摘されています。
大型掘立柱建物 -三内丸山遺跡のランドマーク-

三内丸山遺跡のランドマーク的存在である、遺跡内の北側に位置する大型掘立柱建物は、柱穴の直径、地面に掘られた深さ共に2m、縦方向に三層の構造を持っている(三階建て)という、高さ約20メートルの大型建物です。

復元された建物のすぐそばに位置するドーム内では柱穴が再現されているのですが、かなり大きいものであることがわかります。

用途としては物見櫓、灯台、神殿等々、多方向へ広がりつつの推定がなされてはいるようです。
“三内丸山遺跡”の名前を知らなかったとしても、建物の写真を見ると「あぁ、あの遺跡か!」となることも多そうであるあたり、今も昔も三内丸山を象徴する建物であるという点に、異論はなさそうです。