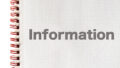雪に埋もれた、縄文人たちの生活跡
3月の三内丸山遺跡
雪の中の縄文時代

積雪シーズン真っ盛りの酸ヶ湯(青森県内の豪雪地です)のような状況が用意されていたわけではなく(※1)、南関東の感覚でいうところの”10年に一度レベルの大雪”という感じだった、三月の三内丸山遺跡。
最寄駅は、JRの新青森駅です。

現地の人曰く「全然、全然。このくらいじゃ積もったうちに入らないですよ 笑」とのことでしたが、概ね数十センチ程度。この量が大体一晩で降ったようです。

「なるほど、やっぱりそういうものなんですね」などと表向き納得しつつ、頭での理解とは別に、そうはいってもやっぱり結構な量だよな、などと思ってしまうのが本音ではありました。
実際2014年の大雪が、横浜市内だとこれより少し少ない位でしたからね。
やや遠くに見えるのは三内丸山遺跡のシンボル、大型掘立柱の建物の上層部です。
雪景色の中の三内丸山遺跡は、対象とする時代こそ異なりますが、雪の季節の”北海道開拓の村”(開拓時代の北海道の建物を移築・再現した、野外博物館です)と同種の風情を感じさせます(※2)。
静かで厳しい自然の中で生きる人々の力強さ、素朴で暖かい”なつかしさ”などが、どこか心に染み入るように伝わってくるんですよね。
参考
- 【たびキュンパスで三内丸山へ/5】青森駅前エリアでの昼食後、三内丸山遺跡まで
- Googleマップ “酸ヶ湯温泉“
- 【大雪/国内最速】豪雪地帯・青森の酸ヶ湯で今年初の積雪4メートル超えを記録(※1)
- 【00年代の札幌】野外博物館 北海道開拓の村(新札幌駅最寄り、野幌森林公園隣)(※2)
- 北海道開拓の村公式サイト(※2)
“三内丸山集落”の成立
それはさておき。
12000年前(ないしは16000年前)から始まり約1万年間(あるいはそれ以上)続いたとされる縄文時代の中でも、当時を生きた人々が三内丸山で集落を営んでいたのは約5900~約4200年前、縄文時代の前期から中期にかけての時期に該当します(縄文時代内部の時代区分については後述します)。
この時期より以前の津軽海峡周辺エリアでは、既に大平山元遺跡(縄文時代草創期、青森県東津軽郡外ヶ浜町)や北小金貝塚(同前期、北海道伊達市)などでの生活痕が確認されていますが(※1)、その上で約5900年前に突然訪れた温暖化が動機となって人々が三内丸山に集い、約4200年前には突然訪れた寒冷化によって人々が集落を放棄することになった、と考えられている形ですね。
ちなみに、この時三内丸山の人々を動かした温度差は、気温・水温とも2℃だったようです(※2)。
昨今言われる”温暖化”では、ここ100年で地球上の年平均気温が0.7度上がったということで警鐘が鳴らされていますが、当時の地球上ではその約3倍にあたる温度変化があった、つまり地球環境的には大変動があったということですね(※3)。
2℃の温暖化によって人々が集い、2℃の寒冷化によって人々が集落を放棄することになったという”縄文時代の三内丸山”が機能していたのは、ざっくり取って概ね5000年前。
パッとこの”かつての集落”の姿を見せられた時のイメージとして、「こういう形での生活、今でもやろうと思ったらやれないことはなさそう」(むしろなんか楽しそう)などと思えてしまう部分もなくはないだけに、却って”1万年に渡る悠久の時代”が理解できなくなる感じでしょうか。
なまじ“パッと見の姿”を理解出来る部分があるだけに(今でも、森の中なんかでこんな感じの家を一からDIYしてる人、特に海外のYouTuberなんかにボチボチいるよねみたいな)、どこか“ついこの前まで存在していた姿”かつ”今でもどこかで存在していそうな姿”として見てしまう部分が無きにしも非ずなんですが、ところがどっこい、これは約5000年前の集落が復元された姿ですということで、このあたり大体脳みそがバグり始める瞬間ですね。
「今から5000年前の時点で、既にここまでやれていたのか」と。

“雪景色”と言う部分で惜しむらくは、雪に降られてしまうと折角遺された跡が見えづらくなってしまうという不利が生じてしまうところで、冬の積雪期以外であれば、ここに復元された環状配石墓(※4)が見れたとのことです。
いい塩梅の風情を感じはしたものの、雪の季節にはこういうデメリットもあるんですね。
参考
- 東奥日報社『特別史跡 三内丸山遺跡』(2021.9.13)(※1)
- 外ヶ浜町公式サイト “世界文化遺産 史跡 大平山元遺跡とは“
- 世界遺産 北海道・北東北の縄文遺跡群 “北黄金貝塚“
- Googleマップ “大平山元遺跡“、”北小金貝塚“
- 東京大学 大気海洋研究所 “三内丸山遺跡の盛衰と環境変化 -過去の温暖期から将来の温暖化を考える-“(※2)
- 気象庁公式サイト “地球温暖化について“(※3)
- 全日本民医連 “地球温暖化を止めよう(1) 1℃や2℃でなぜ騒ぐ? ~温暖化のいま(上)“(※3)
- Google画像検索 “環状配石墓 三内丸山遺跡“(※4)
- 青森県教育委員会 “特別史跡 三内丸山遺跡”(史跡パンフレット)
- NPO法人三内丸山縄文発信の会 “さんまる探訪 三内丸山遺跡ガイドブック(改訂版)”(ものの芽舎、2021.10.13)
雪景色と三内丸山遺跡

言われてみると、そこかしこにそれっぽい盛り上がりが、

いくつか、姿を見せていました。

右が大型竪穴住居、左が大型掘立柱建物です。共に順路の最終盤に位置していますが、

まずは順路に沿って、”日本のかつて”が復元された世界へ進みます。
縄文時代”一万年”の内訳と、三内丸山遺跡
| 区分 | 時期 |
| 草創期 | 約16000~11500年前(※1) |
| 早期 | 約11500~7200年前 |
| 前期 | 約7200~5400年前 |
| 中期 | 約5400~4400年前 |
| 後期 | 約4400~3000年前 |
| 晩期 | 約3000~2700年前(※2) |
縄文時代は約12000年間が6期に区分されていますが、その始まりの時期と終わりの時期については諸説あります(表中の赤字=三内丸山遺跡で集落が営まれていた時期)。
最も無難、というかすわりがいいのは「縄文土器が出現した約12000年前ごろはじまり(近年の有力説)、弥生時代が始まった約2300年ごろ終わった」と捉える区分でしょうか。
その場合約9700年、都合一万年ということになりますが、このほか、
始まり(※1)については
- 約1万6000年前:温暖化による環境変化や、弓矢・土器の使用開始などを基準とする説による
対して、終わり(※2)については
- 約3000年前:稲作の開始などを基準とする説による
とされる見方も存在します。
そのため、最短で9000年(約1万年)、最長で13700年間続いた形が出てくるという、少々のばらつきが生まれます。
参考