この記事を読むのに必要な時間は約 8 分13秒です。
神奈川県立歴史博物館特別展 “洞窟遺跡を掘る(海蝕洞窟の考古学)”
三浦半島と海蝕洞窟
洞窟とは、地下にある空間のうち入り口の大きさよりも奥行きが深いものを指しますが、このうち海の波によって崖面が削られた洞窟が海蝕洞窟と呼ばれます。
四方を海に囲まれた日本では全国各地に存在するタイプの洞窟ですが、三浦半島では1924年に初めて東京湾沿い(横須賀市鳥が崎)にて発見されて以来発掘調査の対象となっていて、弥生時代から古墳時代にかけて使われていた道具が数多く出土しています。
今回の特別展『洞窟遺跡を掘る』では、三浦半島(東京湾沿いと、特に南端)の海蝕洞窟にて出土した原始時代の人類の生活の跡が、多数展示されていました。
特別展 “洞窟遺跡を掘る(海蝕洞窟の考古学)”
出土作業関連
会場内の様子

特別展示室に入るなり”工事中”の雰囲気を醸すカラーコーンと立ち入り禁止バーで作られた一画があるので、一見しただけだと、なんとなく「準備中コーナーがあるのかな」ということが伝わってくるのですが、
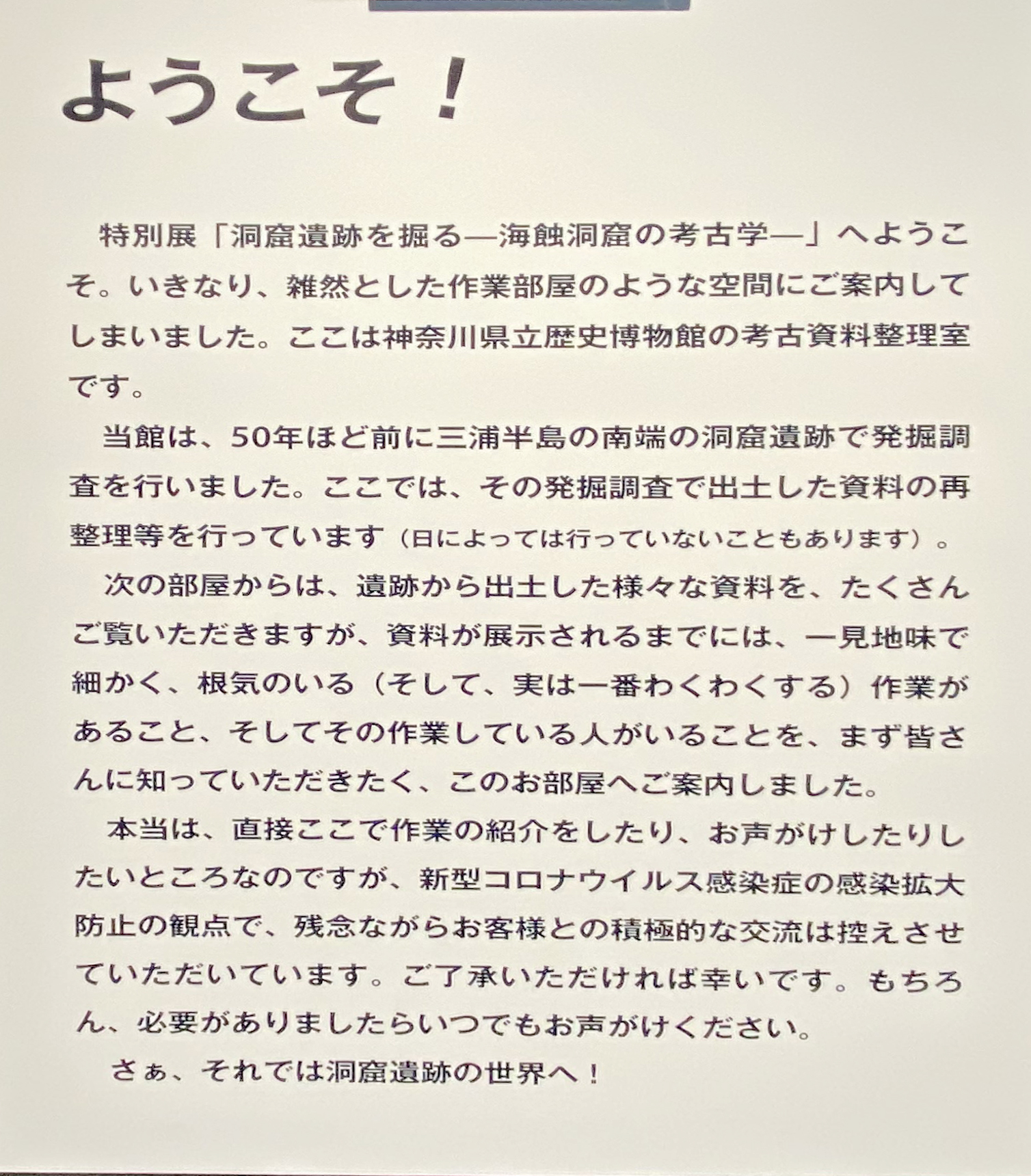
実は展示はここから始まっています。

出土したあとに振り分けられた出土品と、

作業に使う道具等々。
このライブ感強めの展示も演出のうちですということで、展示品が一気に身近なところに引き上げられた上で出土品が展示されたコーナーへと続きます。
先史と歴史、放射性炭素年代測定法
未だ人類の祖先が文字を使用していなかった時代は、”人類が文字を使用する前の時代”、つまり文献資料で解釈することが出来る”歴史”時代に先立つ時代だったということで先史時代(=原始時代)と呼ばれます。
目下のところ、先史時代を生きた人々のあり方はその生活跡(遺跡や出土品の様子)から推定されていますが、”推定”にあたっては、出土品が使われていた時期を知るための手段として”放射性炭素年代測定法“が用いられています。
放射性炭素年代測定法では、本来その出土品に含まれているはずの”ある特定の成分”の残存量を調べることによって出土品の”鮮度”を明らかにしますが、ここでいう”ある特定の成分”とは、自然界にごく微量存在する炭素の同位体(同位体について、後述)である14Cのことです。
手短に言うなら、14Cの”減り具合”(減り具合について、後述)によって出土品の作られた年代を推定できるというのが、放射性炭素年代測定法の持つ理屈に当たります。
14Cと”同位体”、半減期
同位体とは、原子核の構造が通常の原子とは異なる(=中性子の数が異なる)原子の呼称ですが、炭素原子には通常の炭素原子(12C)の他、中性子数の異なる二つの原子(13Cと14C)が存在します。
“C”の左斜め上についている”12、13、14″は、それぞれ”陽子+中性子”の数を表しています。
3つの炭素原子12C、13C、14Cの陽子の数はいずれも6個であることに対して、中性子の数はそれぞれ12Cが6個、13Cが7個、14Cが8個と異なっていますが、陽子の数は同じでも中性子の数が異なっているため、異なる炭素原子として表記されているんですね。
この3つの炭素原子のうち特に14C(原子核内に6個の陽子と8個の中性子を持つ炭素原子)は、”元々不安定な状態で自然界に存在しているため、より安定した状態を自発的に目指そうとする“という特徴を持っていますが、14Cの持つ”自発的に安定した状態へ”という特徴は、原子核中の中性子が放射線を出しながら崩壊し、結果として”5730年で元の量の半分が14Cではなくなってしまう(=別の原子に変化してしまう)“という形で表面化します。
放射線を出しながら崩壊していった中性子が陽子となり、12Cの同位体だったはずの14Cは別の原子(原子番号が一つ多いN=窒素)に変化してしまうという特徴に、”死滅してしまった動植物の体内では新たに14Cが補充されることがない”という性質を加味して考えると、14Cの減り方を調べることによって、その出土品の年代を特定することが可能となるんですね。
この点少し補足すると、原子番号はそれぞれ炭素(C)が6、窒素(N)が7です。
14Cの中性子が一つ減り、陽子が一つ増えたことによって、元・14Cだった原子の中性子数・陽子数はどちらも7個となりますが、表現を変えると、経年によって(放射線を発しながら崩壊する)14Cは14N(陽子数7、中性子数7)へと変化することになる、減った炭素は窒素へと姿を変えるのだということです。
ちなみに、14Cは”原子核中の中性子が放射線を出しながら崩壊する”という特徴を持つことから放射性同位体と呼ばれ、後者の(5730年で元の量の半分が14Cでなくなってしまう)特徴(期間自体)については”半減期“と呼ばれます。
動植物の体内に取り込まれた14Cは、例えていうなら、その動植物が死滅した瞬間にスイッチが入るストップウォッチのような役割を果たしているのですが、現在のところその成分におよそ炭素を含むものであれば全て、放射性炭素年代測定法による測定の対象物とすることが出来ます。
余談として、今では考古学等の世界で当たり前のように利用されているこの方法(放射性炭素年代測定法)は、カリフォルニア大学バークレー校のウィラード・リビー博士によって1949年に開発され、同博士はこの業績によって1960年にノーベル化学賞を受賞しています(THE NOBEL PRIZE “Willard F. Libby“)。
原始時代の道具の使用・進化
打ち砕くだけで作れられた打製石器の時代(旧石器時代)を経て、やがて道具そのものが研磨して作られた磨製石器の時代へと続きますが、磨製石器の時代(新石器時代=縄文時代や弥生時代)には、土器や骨角器も併用されました。
それぞれ地質年代による区分では、旧石器時代は更新世に、新石器時代は完新世に該当します。
氷期と間氷期を繰り返していた”氷河期”=更新世が終わりを迎えた完新世への移行期には、多くの氷床が融解し、地球上で海面が上昇しました。この大きな環境変化によって、それ以前の人々の生活拠点の多くは海底に沈むこととなったため、”氷期の終わり”はまた、地表のみならず当時を生きた人類の祖先にも大きな節目をもたらすこととなります。
この点、更新世から完新世へという地質年代上の大きな節目が、旧石器時代から新石器時代へという人類史の大きな節目を作ることになったのだ(地質学的な大変革が原因となって、人類史の大きな節目を作ることになったのだ)という因果関係が、双方の間に存在します。
氷期の終わりが人類の生活・歴史を大きく変化させたのだ、ということですね。
縄文時代の中期(完新世)には再び地球規模の寒冷な時期が訪れますが、概して気候自体も温暖なものとなって行ったことから毎日の生活環境はより安定した状態へと移り変わり、当時を生きた人々の間では定住化が進みます。このことによって、使用される道具にも、単なる実用的な機能を超えた要素(主に当時を生きた人々の間のコミュニケーションがもたらしたと推定される、”飾りつけ”要素)が含まれるようになっていきました。
「ただ単に道具として使えればいい」という状態から、「どんな道具を使っているのか」という点にも目が向けられるようになっていくのが、新石器時代以降の道具の特徴です。
同時に、狩猟の対象が大型動物から小型動物に変化するなど、気候の変化と共に食生活も変化したため、使用する道具にしても”変化”に対応したものが登場しますが、いずれの時代の道具も、毎日の生活の中から人力で可能な範囲での改良が繰り返されることになるため、長い時間をかけたゆるやかな成長が特徴として挙げられます。
出土品の展示
弥生時代の三浦半島

弥生時代の三浦半島では、既に現生人類の祖先による活発な活動が行われていたようです。

弥生時代の特徴というと”農耕生活が定着したこと”がしばしば挙げられますが、だから狩猟が無くなったのだ(逆に縄文時代には農耕が行われなかったのだ)とはならず、狩猟は狩猟で並行して行われていました。
同様に、縄文時代にも農耕は行われていたようですが、定住生活が進まなかったため、それが定着することが無かったというのが正確なところのようです。
三浦半島では特に海での漁も活発に行われていたようで、海産物を用いた道具の展示や、食べた後に残された貝殻や骨などの展示も行われていました。
磨製石器

ただ単に打ち砕かれただけではなく、磨かれた跡が見える磨製石器が、

石斧と共に展示されていました。
尖頭器・石鏃・貝刃

ちなみに弥生時代の三浦半島では、海産物だけではなく野生動物も食用とされていたようで、旧石器時代から使われている尖頭器や打製の石鏃(せきぞく。矢の部分)と磨製の石鏃、

さらには貝殻が道具として使われた貝刃なども展示されていました。石鏃は、道具としては縄文時代の草創期以来使われている道具ですが、その道具が進化している様子も見て取れます。
三浦半島の遺跡の出土品の特徴としては、貝殻に関するものが多いことも挙げられるようですが、貝刃は、貝殻の縁がのこぎり状に加工されたものです。このほか、貝包丁や匙形の貝も出土されているようです。
弥生土器・土師器・須恵器

土器の展示では、日常生活用途として使われた土師器や、

祭祀用・副葬品として用いられた須恵器の他、

さらには弥生中期(紀元前5世紀から3世紀半ば)に作られた弥生土器など。
日常に土器が用いられて久しくなった時代に使用された土器の展示もありました。
弥生土器は、縄文土器に比べて薄型で硬く、赤褐色をしていることに特徴があるとされていますが、今から約5000年ほど前に誕生した縄文時代中期(5000年~4000年前)の縄文式土器に比べると、その違いが一目瞭然です。
縄文土器については箱根の箱根美術館などに展示がある他、縄文土器を代表する”火焔型土器”の”火焔”の名が、日本で初めて出土された新潟県内で”信濃川火焔街道“(日本遺産 火炎型土器 “信濃川火焔街道 縄文の旅“)として用いられています。
卜骨・勾玉

日常生活まわりの道具から毎日の生活のあり方が推定されるほか、他地域からの文化の流入や当時の交易状況を思わせるものとして、動物の骨を使った”骨占い”で用いられた卜骨や、

ヒスイで作られた勾玉(装身具)の展示もありました。
卜骨を使った占いは中国大陸から伝わり、弥生時代の日本で広まったものだといわれていますが、その出土から推察されることとしては、この場合大陸経由の文化が三浦半島にまで伝わっていたということが挙げられます。
このほかに日本海側(新潟県糸魚川市の姫川流域)の特産品であるヒスイを用いた勾玉が出土しているということからは、この時代の日本列島では、既に日本海側と太平洋側をつなぐ交易ルートが開拓されていたということが明らかになります。
旧石器時代であれば人々が移住を繰り返して生活していたところ、新石器時代(縄文時代や弥生時代)には人々の定住化が進んだ上で物流が発達していったというところに、その時代固有の特徴が見出されています。
(参考:神奈川県立歴史博物館 『特別展 洞窟遺跡を掘る 海蝕洞窟の考古学』)

